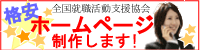05弁理士試験
1.弁理士試験とは
弁理士試験は、工業所有権に関する専門家である「弁理士」を選定する国家試験です。所管は経済産業省・特許庁が行い、毎年一回実施されます。
弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標などの権利取得を図るなど、知的財産分野で高度な専門知識と実務能力が求められる職種を担います。
2.受験資格
学歴・年齢・国籍・性別などの制限は一切なく、誰でも受験可能です。
また、特許庁で審査官・審判官として5年以上勤務した者や弁護士資格を有する者などは、試験合格後、実務修習を経ることで弁理士登録できる規定もあります。
3.試験日程(例年のスケジュール)
試験は例年以下の時期に実施されます。正式な日程は毎年1月頃に官報で告示され、特許庁ホームページに掲載されます。
願書交付・出願受付:2月上旬〜3月中旬
インターネット・郵送等により受付
短答式試験:5月中旬(日曜日)
12:30〜16:00(3時間30分)
論文式試験(必須科目):6月下旬(日曜日)
工業所有権に関する法令(特許・実用新案、意匠、商標)
論文式試験(選択科目):7月下旬(日曜日)
理工系または法律の科目の中から1科目を選択
口述試験:10月中旬〜下旬
東京で実施、日程は数日間設定
最終合格発表:10月下旬〜11月上旬
官報および特許庁HPで公表
4.試験地
各試験の開催地は以下の通りです:
短答式:東京・大阪・仙台・名古屋・福岡
論文式:東京・大阪
口述試験:東京のみ
令和7年度は各試験地や会場が官報・特許庁HP等で正式発表予定です 。
5.受験手数料
特許印紙12,000円
6.試験内容(詳細)
構成:三段階方式
弁理士試験は以下の構成で行われます:
短答式筆記試験(一次試験)
論文式筆記試験(二次試験)
必須科目(工業所有権)
選択科目(技術系または法律系)
口述試験(三次試験)
A.短答式筆記試験(一次試験)
実施時期:5月中旬~下旬(2025年は5/18)
形式・出題数:五肢択一、全60問、マークシート方式
試験時間:3時間30分(12:30〜16:00)
出題科目と出題数:
特許法・実用新案法:20問
意匠法:10問
商標法:10問
工業所有権に関する条約:10問
著作権法・不正競争防止法:10問
合格基準:過去実績では得点率65%、かつ各科目ごとの足切り基準(例:科目40%)
B.論文式筆記試験(二次試験)
一次試験合格者(または該当免除者)が対象となります。
必須科目:工業所有権に関する法令(特許・実用新案、意匠、商標)
試験科目:
特許・実用新案法(2時間)
意匠法(1.5時間)
商標法(1.5時間)
試験時間:
特許法等:10:00–12:00、意匠:13:15–14:45、商標:15:30–17:00
形式:論文形式。試験時に該当する法文が貸与されます
合格基準:必須科目全てにおいて個別の基準点以上獲得
選択科目(1科目選択)
選択肢:理工系(機械・化学・情報など5分野)または法律(弁理士業務関連法)
実施時期:選択科目は7月下旬
形式・時間:論文式、90分
合格基準:必須科目と同様に個別基準達成が必要
C.口述試験(三次試験)
対象:論文式試験合格者
実施時期:10月中旬~下旬
実施地:東京
形式:面接形式。試験官と短時間質疑応答(対象科目:工業所有権関連法)
合格率:例年90%以上と高水準
7.合格後の流れと研修
a. 最終合格発表
口述試験合格後、合格者氏名が官報および特許庁HPで正式に告示されます(例年10月下旬〜11月上旬)
b. 実務修習
合格後に、日本弁理士会が実施する実務修習(特許庁指定)を修了することが義務付けられています。
修習は通常6か月~一年程度で、実務経験および法務処理能力を培います。
c. 弁理士登録
実務修習修了後、日本弁理士会への入会申し込みを行い、登録すれば、正式に弁理士として業務が可能になります。
8.資格取得のメリット
知的財産専門家として活躍可能
特許・実用新案・意匠・商標など、幅広く高度な法務処理が可能に。
独立開業または企業勤務、選択肢の自由
特許事務所・企業法務部門・法務コンサル等での就職・独立も可
高い社会的評価と報酬水準
難関試験でありながら職務の専門性が高く、キャリア・報酬面で魅力的。
多種多様な業務領域に対応
技術分野(理工系)にも強い専門士業として、異業種との架け橋に。
キャリア平均:社内異動・出世につながる
企業勤務中に合格した受験生は、他部門への転属・昇進につながるケースもある。
9.まとめ
誰でも受験可能な三段階(短答→論文→口述)試験であり、幅広く高度な専門知識が試されます。
試験日程は5月短答、6〜7月論文、10月口述、11月合格発表(官報・HP)です。
合格後は実務修習と登録が必要で、これを経て弁理士として正式に業務を開始できます。
メリットとしては、専門士業としての社会的信用・独立・企業法務など多様なキャリアパスおよび専門業務が得られることです。
10.ホームページ
特許庁