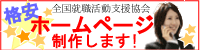14税理士試験
1.税理士試験とは
税理士試験とは、税理士としての業務を行うために必要な専門的知識・技能を有するかを判定する国家試験です。税理士法に基づき、国税審議会が行う筆記試験であり、合格後は日本税理士会連合会への登録を経て「税理士」として活動することができます。 税理士の主な業務は、税務代理(税務申告書の作成や税務署とのやりとり等)、税務書類の作成、税務相談などであり、企業や個人の税務を支える専門家として極めて重要な役割を担っています。独立開業できる国家資格として人気が高く、また経営や会計の専門家として、企業内税務やコンサルタントとしての活躍も期待される職種です。 試験は科目合格制を採用しており、一度にすべての科目に合格する必要はありません。年度ごとに科目を積み重ねて合格を目指すことができる点も、働きながら受験する社会人にとっては魅力の一つといえます。
2.受験資格
税理士試験を受験するためには、以下のような一定の学歴や実務経験、あるいは資格の取得が必要です。
(1)学歴による資格
大学または短大等で「社会学」に属する科目を1科目以上履修し、卒業した者
上記科目を履修し、一定の単位を取得している大学3年次以上の者(在学中受験可)
(2)資格・職歴による資格
日商簿記検定1級または全経上級の合格者
法人等の会計事務、銀行等の一定業務、税理士・弁護士等の補助事務に2年以上従事
このように、法律・経済系の学歴や実務経験、あるいは関連資格の取得により受験資格が与えられます。上記は主なものであり、詳細は国税庁が毎年発行する「受験案内」に明記されています。
3.試験日程(例年のスケジュール)
税理士試験は年1回、例年8月上旬~中旬の3日間にわたって実施されます。受験申込は春頃に行われ、試験は夏、合格発表は冬(11月以降)に行われるのが通例です。
【例年のスケジュール】
受験申込:4月上旬〜中旬
試験実施:8月上旬~中旬(3日間)
合格発表:11月以降
試験は平日に行われるため、社会人受験者は試験休暇の取得や業務調整が必要です。科目合格制のため、初年度は1~2科目から受験し、数年かけて全科目合格を目指すスタイルが一般的です。
4.試験地
税理士試験は全国各地の主要都市で実施されています。試験地は受験申込時に選択することができ、例年以下のような都市が試験会場となっています。
【主な試験地】
札幌・仙台・高崎・さいたま・東京(複数)・金沢・名古屋・大阪(複数)・広島・高松・福岡・熊本・那覇(以上令和7年度の場合)
受験者数の多い地域では複数会場に分かれることもあり、最終的な会場は受験票にて通知されます。公共交通機関のアクセスが良好な場所が選ばれることが多く、全国の受験者にとって利用しやすい体制となっています。
5.受験手数料
受験手数料は、受験申込科目数に応じ、次のとおりとなっています。
| 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000円 | 5,500円 | 7,000円 | 8,500円 | 10,000円 |
6.試験内容(詳細)
税理士試験は、全部で11科目の中から5科目を選択して受験します(免除制度あり)。必須科目2科目、選択必須科目1科目、選択科目2科目の構成です。
【必須科目】
簿記論
財務諸表論
この2科目はすべての受験者が受験する必要があります。簿記論は仕訳や帳簿の作成、財務諸表論は財務諸表の作成と会計理論に関する知識を問う試験です。
【選択必須科目】(1科目選択)
所得税法
法人税法
どちらか1科目を選択し、受験します。受験者の多くは法人税法を選ぶ傾向があります。理由として、業務上の需要が高く、試験問題の傾向が比較的安定している点が挙げられます。
【選択科目】(2科目選択)
以下の科目から2科目を選択します。
相続税法
消費税法又は酒税法
国税徴収法
住民税又は事業税
固定資産税
この中でも、相続税法と消費税法の受験者が多く、実務的にも需要の高い科目となっています。一方、酒税法や住民税、事業税は受験者数が少ないものの、難易度が比較的低めとされ、戦略的に選択されることもあります。
試験形式
すべての科目が記述式(理論+計算)で行われます。試験時間は1科目あたり2時間で、理論問題(論述形式)と計算問題の両方が出題されます。
【出題の傾向】
理論問題:条文理解、体系的な記述力が問われます。
計算問題:速さと正確性が求められます。計算量は非常に多いです。
合格基準は、各科目とも満点の60%とされていますが、相対評価で調整が入ることもあります。
合格率
税理士試験は非常に難易度の高い試験として知られています。科目ごとの合格率は10~20%程度であり、全科目合格までには平均して5~7年程度かかると言われています。ただし、毎年1~2科目ずつ着実に合格を積み重ねることで、確実にゴールへ到達することができます。
7.合格後の流れと研修
税理士試験において5科目すべての合格を達成した後は、税理士として登録するために、所定の手続きが必要です。
【税理士登録要件】
以下のいずれかを満たしている必要があります。
実務経験2年以上(税務・会計業務)
所定の大学院修了による一部免除を受けた者
実務経験がない場合には、税理士事務所などでの実務に2年以上従事する必要があります。
【税理士登録手続】
日本税理士会連合会に申請し、必要書類と登録料を提出します。その後、税理士証票が交付され、正式に「税理士」として業務を行うことが可能となります。
【研修】
登録後は、税理士会主催の研修(倫理研修、実務研修)への参加が求められます。また、継続的な自己研鑽として税制改正への対応も含めた知識のアップデートが不可欠です。
8.資格取得のメリット
税理士資格の取得には多くの努力が必要ですが、その分得られるメリットも非常に大きなものがあります。
独立開業が可能:国家資格として、個人で事務所を開設し、独立することができます。
高い専門性と社会的信頼:企業・個人の税務を担う重要な存在として、高い信頼性を有します。
収入面での安定・上昇:経験を積むことで顧客数や業務範囲が拡大し、高収入も実現可能です。
企業内でも評価される:税務部門・経理部門において、税理士資格は強力なスキル証明となります。
一生モノの資格:更新不要であり、一度取得すれば生涯有効な国家資格です。
9.まとめ
税理士試験は、わが国における税務の専門家を養成するための国家試験であり、極めて高い専門性と倫理性が求められます。合格までの道のりは長く、厳しいものではありますが、科目合格制という柔軟な制度により、自分のペースで挑戦を続けることができます。
独立開業や企業内での活躍、さらにはコンサルタント業務など、活用の幅が広い点も税理士資格の魅力です。税法改正に敏感な現代社会において、信頼される税のプロフェッショナルとして、将来の安定したキャリアを築きたい方にとって、税理士試験は大きな価値のある国家資格といえるでしょう。
10.ホームページ
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm