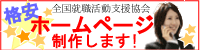15公認会計士試験
1.公認会計士試験とは
公認会計士試験は、財務書類の監査および会計に関する高度な専門知識を有し、企業や団体の経済活動を監視・支援する専門家である「公認会計士」になるための国家試験です。金融庁の下に設置されている公認会計士・監査審査会が所管し、日本で最も難易度の高い資格試験の一つとされています。
公認会計士は、企業の財務情報の適正性を検証する「監査業務」のプロフェッショナルとして、主に監査法人や会計事務所に所属して活動します。また、近年では企業の会計・税務部門、コンサルティング業務、さらにはIPO(新規株式公開)支援など、活躍の場は広がっています。
公認会計士試験は、段階的に学力を評価する仕組みとなっており、「短答式試験」と「論文式試験」の2段階で構成されています。合格後は実務経験や研修を経て、最終的に公認会計士登録を行うことで、公認会計士となります。
2.受験資格
公認会計士試験は、年齢・学歴・職歴に関係なく、誰でも受験することができます。つまり、特定の大学卒業や資格保有がなくても、知識さえあれば受験可能です。
ただし、試験範囲が非常に広く、かつ高度な専門知識が問われるため、大学・大学院や専門学校などで体系的な学習を経たうえでの受験が一般的です。特に経済学部・商学部・法学部などに在籍する学生が、在学中に合格を目指すケースが多く見られます。
3.試験日程(例年のスケジュール)
公認会計士試験は、1年に1回実施される国家試験です。試験は「短答式試験」と「論文式試験」に分かれており、それぞれの実施時期は以下のとおりです。
【短答式試験】
12月中旬頃(第1回)と翌年5月下旬頃(第2回)の年2回
合格者は翌年、翌々年の2年間は短答式試験を免除され、論文式試験を受験することができます。
【論文式試験】
8月下旬頃(3日間連続)
【合格発表】
短答式:1月下旬および翌年6月中旬頃
論文式:11月中旬頃
短答式試験は年度をまたいで2回実施されますが、合格後は「論文式試験」の受験資格を得ることになり、2年間の間に論文式に合格すれば最終合格となります。
4.試験地
公認会計士試験は、全国の主要都市に設置された試験会場で実施されます。短答式試験と論文式試験では、実施会場が異なる場合もあります。
【主な試験地】
札幌
仙台
東京
名古屋
大阪
広島
福岡
受験者数の多い地域(東京・大阪など)では複数の会場が設けられることがあり、受験票で指定された会場で受験することになります。試験当日は、交通機関の遅延対策や感染症対策が講じられる場合もあるため、最新の受験案内に目を通しておく必要があります。
5.受験手数料
19,500円6.試験内容(詳細)
公認会計士試験は「短答式試験」と「論文式試験」の2段階で構成されており、順に突破していく必要があります。出題範囲は広く、会計、監査、企業法、経済学、租税法など、ビジネス全般を網羅する内容となっています。
(1)短答式試験
短答式試験は、マークシート形式で実施される筆記試験です。以下の4科目が出題され、全体で70%程度の得点が合格基準とされます。
財務会計論(理論・計算)(40問以内)
管理会計論(20問以内)
監査論(20問以内)
企業法(主に会社法)(20問以内)
各科目の出題数は多く、計算問題と理論問題のバランスが重視されます。財務会計論・管理会計論では、仕訳や財務諸表の作成、意思決定分析など、正確な計算力が求められます。一方、監査論・企業法では、条文理解や判断力が問われます。
短答式試験の合格者は、「短答式合格者」として認定され、その資格で論文式試験に進むことができます。
(2)論文式試験
論文式試験は、記述式の問題に対して論述や計算を行う試験です。3日間にわたり、7科目の試験が実施されます。
【必須科目】
会計学(財務会計論+管理会計論)
監査論
企業法
租税法
【選択科目(以下のうち1科目)】
経営学
経済学
民法
統計学
出題内容の概要
会計学:貸借対照表・損益計算書の作成、会計基準の解釈、原価計算や予算管理など、非常に幅広く出題されます。計算と理論のバランスが鍵となります。
監査論:監査基準、内部統制、監査手続などに関する問題が中心です。
企業法:会社法を中心に、商法・金商法に関する条文理解と事例問題への対応が必要です。
租税法:法人税、所得税、消費税などに関する理論と計算が出題されます。
選択科目:自身の得意分野を選び、理論的・実践的な知識を活かして解答します。
論文式試験では、時間配分と答案構成が重要です。記述力、思考力、スピードのすべてが問われる試験であるため、答案練習を繰り返して対策を行うことが合格への鍵となります。
7.合格後の流れと研修
論文式試験に合格すると、「公認会計士試験合格者」としての資格を得ることができますが、直ちに公認会計士を名乗れるわけではありません。以下のプロセスを経て、正式な登録が行われます。
(1)実務経験(業務補助等)
会計監査を主とする業務に、通算して3年以上従事することが必要です。多くの場合、監査法人に就職し、アシスタントとして監査業務に携わりながら実務経験を積んでいきます。
(2)実務補習
日本公認会計士協会が実施する「実務補習所」で、3年間の補習を受けます。これは週末や夜間に実施され、業務と並行して受講する形になります。
(3)修了考査
実務補習の3年間の修了時に「修了考査」が行われます。これは最終的な知識確認の位置づけであり、これに合格することで「公認会計士」として登録申請が可能になります。
(4)登録と就業
修了考査合格後、日本公認会計士協会に登録を行い、正式な公認会計士としての資格を得ます。その後は、監査法人勤務、独立開業、企業のCFO、コンサルタントなど、さまざまなキャリアパスが広がります。
8.資格取得のメリット
公認会計士資格の取得には、以下のような多くのメリットがあります。
社会的信頼性と専門性の証明
高い専門性と倫理性を兼ね備えた資格であり、企業・社会からの信頼が厚い資格です。
高収入が期待できる
監査法人では年収1,000万円超も可能で、キャリアを積むごとに報酬も上がります。
活躍のフィールドが広い
監査業務にとどまらず、M&A、事業再生、企業経営支援など多方面で活躍できます。
国際的な資格との親和性
USCPA(米国公認会計士)など、他国資格とのダブルライセンスも視野に入ります。
将来の独立・起業も可能
コンサルティング会社の設立や監査法人の開業など、自分の裁量で働くことも可能です。
9.まとめ
公認会計士試験は、極めて高い専門性を持つ国家資格であり、難易度も相応に高いですが、それに見合うだけの社会的地位とキャリアの選択肢が待っています。会計・財務・監査という経済の根幹に関わる分野で活躍したいと考える人にとって、公認会計士資格は最適な道のひとつです。
短答式試験・論文式試験の二段階を突破し、さらに実務経験・補習・修了考査というプロセスを経て、初めて名乗ることができる「公認会計士」、その責任とやりがいは大きく、将来を見据えた確かなキャリアを築く上で、非常に価値のある資格といえるでしょう。
10.ホームページ
金融庁