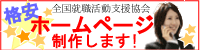18簿記能力検定試験
1.簿記能力検定とは
「簿記能力検定試験」は、公益社団法人全国経理教育協会(全経)が主催し、文部科学省後援のもと実施されている公的検定です。「全経簿記能力検定」とも呼ばれます。
試験は 上級・1級・2級・3級・基礎簿記会計の計5区分があり、構成する科目や難易度が異なります。
特に上級合格者は、税理士試験の受験資格が得られることから、会計分野を志す人にとって登竜門的検定となっています。
2.受験資格
受験資格には制限がなく、誰でも自由に希望する級を受験することができます。
3.試験日程(例年のスケジュール)
例年、試験は 年4回 実施されますが、等級により実施回数が異なります:
上級:7月中旬・2月中旬の年2回実施
1級・2級・3級・基礎:5月下旬・7月中旬・11月下旬・2月中旬の年4回実施
申込期間は検定の約1か月前から数週間ほどで、5月検定なら4月上旬~中旬、7月検定は5月下旬~6月中旬、11月検定は9月下旬~10月下旬、2月検定は12月下旬~1月中旬となっています。
4.試験地
試験地は 全国各地の専門学校等指定会場で実施されます。
また、2級商業簿記・2級工業簿記・3級・基礎簿記会計については ネット試験(CBT) の形式でも受験可能です
5.受験料
1級 8,800円
2級 5,500円
3級 3,300円
簿記初級 2,200円
6.試験内容(詳細)
区分と科目体系
試験区分と科目構成は以下の通りです:
■上級(4科目)
上級は、簿記能力検定の中で最も難易度が高く、税理士試験の受験資格が得られる唯一の級です。出題は以下の4科目で構成されており、全体合格制となっています。
【商業簿記】
企業における日常の取引(売買、経費、資金調達など)を帳簿に記録する技能を問う科目です。株式発行、社債、リース、外貨建取引、本支店会計など、高度な企業会計処理が出題範囲に含まれます。
【財務会計】
簿記記録をもとに、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)を理論的・体系的に解釈する力を問う科目です。企業会計原則や企業会計基準など、制度会計・財務諸表論の知識も求められます。
【工業簿記】
製造業における材料費、労務費、経費の集計や、製造原価報告書の作成に関する知識を問う科目です。製造指図書、仕掛品、部門別計算など、複雑な原価記録処理が含まれます。
【管理会計(原価計算)】
将来の意思決定や業績評価、コスト削減のための会計的分析を行う能力を問う科目です。標準原価計算、直接原価計算、差異分析、予算管理、損益分岐点分析などが中心です。
上級は全科目を一括して受験し、各科目40点以上かつ合計280点以上(400点満点)で合格となります。日商簿記1級と同程度の難易度で、専門職(経理・会計士・税理士志望)向けの最上位資格です。
■1級(2科目)
1級は上級の手前にあたる級で、以下の2つの科目に分かれています。科目合格制度があり、それぞれ別々に受験・合格できます。
【商業簿記・財務会計】
会社法や会計基準に沿った取引処理、精算表、財務諸表の作成・分析が出題されます。複式簿記の高度な応用力と、財務会計に関する知識をバランスよく問われます。
【原価計算・管理会計】
製造業を想定し、仕掛品や完成品の原価計算、標準原価、直接原価による管理手法などが出題対象です。実務的な原価計算だけでなく、意思決定会計や経営管理の視点も必要とされます。
試験は各科目90分、100点満点、70点以上で科目合格となります。2科目に合格すれば1級全体の合格です。
■2級(2科目)
2級は中級者向けの内容で、経理担当者や初級会計職としての実務能力が期待される級です。こちらも科目合格制度があります。
【商業簿記】
商品売買、手形取引、決算整理などの基本的な取引に加え、固定資産や引当金などの処理も含まれます。損益計算書や貸借対照表の構造を理解し、作成する力が問われます。
【工業簿記】
材料費、労務費、経費などを製造原価に集計し、仕掛品や製品の原価管理を行う力を問う科目です。製造業のコスト計算の導入として、図や仕訳、計算問題を中心に出題されます。
試験は各科目90分、100点満点、70点以上で合格となります。
■3級(1科目)
3級は簿記の入門級で、個人商店や中小企業の日常的な記帳業務を理解する水準です。
【商業簿記】
現金取引、掛取引、売上・仕入、帳簿記入、試算表の作成といった基本的な記帳と集計の技術を学びます。小規模な経営管理にも必要な簿記の基礎的スキルが求められます。
試験は90分、100点満点、70点以上で合格となります。初学者や高校生、社会人の初級者向けに適しています。
■基礎簿記会計(1科目)
基礎簿記会計は全経簿記の中で最も初歩的な級で、簿記未経験者でも対応可能です。
【簿記会計】
単式簿記に近いレベルの記帳練習や、収入と支出の分類、基本的な用語の理解など、概念レベルでの出題が中心となります。簿記の考え方に慣れることを目的としており、職業訓練や導入教育に活用されます。
試験は90分、100点満点、70点以上で合格となります。商業高校の授業や、専門学校の初歩的な簿記講座での成果測定に適しています。実施方式
ペーパー試験:全区分とも基本的には筆記試験(90分/科目)です
ネット試験(CBT):2級2科目、3級、基礎を対象にCBT方式での実施も可能
試験時間
各科目 90分(上級4科目合計は180分相当)
合格基準
上級:各科目40点以上かつ4科目合計280点以上(総点400点中)
1級以下:各科目100点満点中70点以上で合格。科目合格制度あり(2級・1級)
合格率(目安)
上級:約15%前後
1級:商業簿記・財務会計:約40%前後、原価計算・管理会計:約50%前後
2級:商業簿記:約55%前後、工業簿記:約80%前後
3級:約65%前後
基礎簿記会計:約70%前後
7.合格後の流れと研修
合格証書:2級・1級は科目ごとまたは総合で発行されます。上級は総合のみで科目証書はありません
税理士試験受験資格:上級合格者は、日商簿記1級と同様、税理士試験の受験資格が付与されます
研修制度:全経では簿記教育機関が加盟校として試験会場等を提供しており、合格後の研修についての案内は協会および加盟校から提供されるケースが多いです(詳細は協会発表を参照)。
8.資格取得のメリット
公的資格:文部科学省後援の公的検定であり、専門学校等では評価されやすい資格です
進学就職でのアピール:商業・経理分野志望者にとって、履歴書にも記載可能で実務能力を示せます。
税理士試験への道:上級合格により税理士試験の受験資格を取得できる点は最大の強みです
学習のステップ化:級ごとにレベルが整理されており、初学者から上級者まで段階的に学習可能です(基礎→3→2→1→上級)。
9.まとめ
簿記能力検定(全経簿記)は、誰でも受験可能な公的資格試験であり、上級・1級・2級・3級・基礎簿記会計の5区分で構成されています。上級では商業簿記、財務会計、管理会計、原価計算の4科目、1級・2級・3級ではそれぞれ定められた科目があり、科目合格制度も一部に採用されています。
試験は年4回の実施(上級のみ年2回)、会場受験(ペーパー)に加え、2級以下はネット試験も選択可能です。合格基準は級により異なりますが、特に上級合格者には税理士試験の受験資格が与えられる点で、大きな利点があります。学びたいレベルや目的に応じて柔軟に活用できる体系となっています。
10.ホームページ
公益社団法人全国経理教育協会