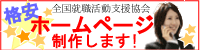19電子会計実務検定
1.電子会計実務検定とは
電子会計実務検定とは、日本商工会議所が主催する資格検定試験で、会計ソフトを用いた会計処理や帳簿作成の実務能力を評価することを目的としています。正式名称は「電子会計実務検定試験」であり、実務の現場で求められるパソコン会計のスキルを体系的に学ぶ手段として注目されています。
近年、企業の会計処理は紙ベースからデジタルへと大きく移行しており、特に中小企業を中心に市販の会計ソフトが幅広く活用されています。そのため、経理・会計部門に求められるスキルも「簿記」だけではなく、「ソフトを使いこなす力」へと進化しています。
電子会計実務検定では、こうしたニーズに応えるべく、簿記の知識と会計ソフト操作の両方を兼ね備えた人材を育成・評価することを目的としています。試験は1級・2級・3級の
3段階で実施されており、実際にソフトを操作しながら仕訳・帳簿作成・決算処理を行うという実践型の内容です。どの級からも受験できます。
2.受験資格
電子会計実務検定には、学歴や年齢、職歴などの制限はありません。どなたでも自由に希望する級から受験することができます。
ただし、各級には想定される習熟度が設定されており、自分の知識やスキルレベルに応じて受験級を選ぶことが推奨されています。また、各級とも簿記の理論、知識が必要となります。
3級:電子会計の初学者向け。パソコン操作の基礎と簡単な仕訳ができるレベル。
2級:日常的な仕訳入力から決算処理までを一通り行えるレベル。
1級:会社全体の取引を会計ソフトで管理し、月次・年次決算を処理できる実務者レベル。
とくに1級では、経理・財務部門における即戦力としてのスキルが求められ、業務の実務経験がある受験者も多く見られます。
3.試験日程(例年のスケジュール)
電子会計実務検定は、年に複数回実施されており、学校や教育機関を中心に実施されています。個人受験はやや少ない傾向にありますが、受験機会は比較的柔軟に設けられています。
【例年の実施スケジュール】
1級は10月の1回のみ(2025年は実施されませんでした。)。他は年2回または3回(6月・11月・2月など)
実施日は各教育機関が設定(統一日ではない)
申込時期:試験の1か月〜2週間前まで(各校で異なる)
学校・専門学校などの「試験実施校」が主体となって実施するため、通学中の学生が最も受験しやすい環境となっています。社会人の場合は、対応可能な会場を探して個別に受験申し込みを行うことになります。
4.試験地
電子会計実務検定は、全国各地の専門学校・商業高校・職業訓練校など、全経認定の「試験実施校」にて行われます。これらの会場には、会計ソフトがインストールされたパソコンが用意されており、実際に操作しながら試験を受ける形式です。
【主な試験地】
北海道から沖縄までの主要都市(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡など)
各地の簿記・経理系の専門学校や大学附属施設
一部の会場では個人申込にも対応
会場の詳細は、公式サイトで確認する必要があります。
5.受験料
1級:10,480円
2級:7,330円
3級:4,200円
6.試験内容(詳細)
電子会計実務検定は、「会計ソフトを用いた実務能力」を評価する検定であり、各級ごとに実技試験が中心となっています。受験に際しては、基本的な簿記知識に加えて、パソコン操作やソフトウェアの基礎理解が前提となります。
【使用会計ソフト】
弥生会計、勘定奉行、会計王、PCA会計など会場により使用できるソフトが決まっています。
(1)3級(初級)
【試験時間】40分
【出題内容】
1. 電子会計データの流れ
2. 電子会計情報の活用
【合格基準】100点満点中70点以上
会計ソフトを初めて扱う方でも取り組みやすい構成で、パソコン操作に慣れていれば短期間の学習で合格を目指せます。
(2)2級(中級)
【試験時間】60分
【出題内容】
1. 関連業務等からの業務データ等の活用
2. 電子会計情報の活用
3. 電子会計データの保管・管理
【合格基準】100点満点中70点以上
実務で想定される処理に近く、経理業務の基礎を一通り経験できる構成です。
(3)1級(上級)
【試験時間】90分
【出題内容】
記述式が中心
1. 電子会計情報の活用
2. 会計ソフトの導入・運用
3. 会計データの電子保存と公開
4. 電子申告・納税システムの理解
5. 企業会計以外の会計システムの理解
【合格基準】100点満点中70点以上
より実践的な内容が問われ、企業会計における実務力を直接評価されます。経理職や経営者の右腕として業務を担う人材に求められるレベルといえます。
【共通事項】
試験形式:すべてパソコン操作による実技試験
採点方法:入力データをもとに自動採点
7.合格後の流れと研修
合格者には、「合格証書」が交付されます。これにより、自身の電子会計スキルを公式に証明することが可能です。
現時点では合格後の義務的な研修制度はありませんが、実務に活かすためには以下のようなステップアップが推奨されます。
日商簿記2級以上の学習:理論面の知識補完として有効です。
税務・経営に関する学習:経理実務との連携が強いため、法人税、消費税、労務管理なども併せて習得すると業務の幅が広がります。
経理ソフトの上級機能の習得:給与連動・部門管理・電子帳簿保存など、より専門性を高める学習へ発展可能です。
また、教育機関では、1級合格者を対象に実践的なインターンシップやOJT形式の研修を設けているケースもあります。
8.資格取得のメリット
電子会計実務検定を取得することで、次のようなメリットがあります。
実務で使えるスキルを証明
「会計ソフトを使える人材」であることを履歴書で明確にアピールできます。
就職・転職活動で有利
中小企業や会計事務所では、即戦力として歓迎されやすくなります。
日商簿記との相乗効果
理論(簿記)と実務(電子会計)の両面を証明でき、バランスの取れた人材として評価されます。
将来的な独立や開業にも有効
小規模事業者向けの記帳代行・税理士補助など、個人事業主としての活躍も視野に入ります。
IT時代に対応した会計力の証明
紙ベースの会計からデジタル化が進むなかで、必須スキルとしての価値が高まっています。
9.まとめ
電子会計実務検定は、デジタル会計の実務力を評価する数少ない資格試験として、近年ますます注目を集めています。簿記の理論だけでなく、実際に会計ソフトを操作して業務を完了させる力が求められる現代において、本検定の取得は大きな強みとなります。
特に中小企業や個人事業主においては、紙の帳簿よりも「弥生会計」などのソフトでの処理が主流となっており、こうした現場に対応できるスキルを備えた人材は、今後ますます需要が高まると考えられます。
就職・転職、あるいは業務効率化を目指すビジネスパーソンにとって、電子会計実務検定は「実務力を可視化する資格」として、非常に有意義な一歩となるでしょう。
10.ホームページ
日本商工会議所