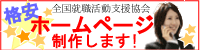20ビジネス会計検定試験®
1.ビジネス会計検定試験®とは
ビジネス会計検定試験®は、大阪商工会議所が主催する検定試験で、財務諸表を理解し、企業の経営状態や課題を把握し、それをビジネスで活用するための「会計リテラシー」を養成することを目的としています。簿記検定と異なり、会計の“作成”よりも、会計情報を“読み解き、分析する力”に重点が置かれているのが特徴です
営業・企画、財務・経理、経営者、公務員、学生など、幅広いビジネスパーソンにとって有用で、新聞・ニュース記事の理解や企業分析など実務的な効果も高いため、注目度が年々増しています。
2.受験資格
受験資格には制限がなく、学歴・年齢・職業・国籍を問わず誰でも受験可能です。連続する2級と3級を同日に併願することもでき、好きな級から受験できる自由度の高さも特長です。
3.試験日程(例年のスケジュール)
年2回、春(3月)・秋(10月)に実施されます。
春(3月)は、すべての級が実施されます。
秋(10月)は、2級と3級が実施されます。
4.試験地
全国の主要都市で受験が可能です。2025–26年度は以下の市が受験地となっています:
札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡
この中から受験地を選択することになります。
5.受験料
1級:11,550円
2級:7,480円
3級:4,950円
6.試験内容(詳細)
ビジネス会計検定は、3級・2級・1級それぞれで出題範囲や形式が異なり、会計読み取り力・分析力・応用力を段階的に評価します。
■出題形式と合格基準
3級・2級:100点満点のマークシート(各70点以上で合格)
1級:マークシート+論述式、200点中140点以上、かつ論述50点以上が合格基準
■3級(基礎レベル)
到達目標: 貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書の構造や基本分析力を習得
出題範囲(主な項目):
財務諸表の基本構成
基本的な分析指標(成長率・安全性・収益性・キャッシュ・フロー・一人当たり分析など)
問題形式: マークシート、2時間
■2級(中級レベル)
到達目標: 連結財務諸表や法規をもとに、より高度な企業分析ができる能力を養う
出題範囲:
財務諸表構造と関連法規(会計制度、開示制度など)
連結財務諸表の理解
応用分析:セグメント、損益分岐点、単位分析など
問題形式: マークシート、2時間
■1級(上級レベル)
到達目標: 概念フレームワークや内部統制など高度な会計理論を踏まえ、企業価値評価まで含む総合力を問う
出題範囲:
会計情報の理論的枠組、開示制度(ディスクロージャー)
注記・補足情報の理解と高度分析
企業価値評価(DCF法・EP法・乗数法など)
問題形式: マーク+論述(2時間30分)、合格基準は論述50かつ総合140点以上
■準1級(認定制度)
1級不合格でもスコア120点以上の得点者には「準1級」と認定する制度が導入されており、スキルを示す指標になります
7.合格後の流れと研修
合格後には、以下の流れに従って手続きやスキル定着が進みます。
成績票ウェブ照会
合格証書の発送
スキル活用と継続学習
多くの受験者が簿記検定、中小企業診断士、証券アナリスト等との併用を推奨し、分析力と会計リテラシーを高めています
8.資格取得のメリット
ビジネスパーソンとしての信頼度向上
会計知識を持つことで説明力や説得力が増し、記事・IR資料の理解にも役立ちます。
就職・転職力アップ
財務データ分析をできる人材として、企業に高く評価されます。
簿記との相乗効果
簿記で財務諸表を“作る力”、ビジネス会計で“読み解く力”を両立できる点が強みです
実務に直結
営業提案、投資判断、経営企画において、数字基準に基づく提案や分析が可能になります。
中上級者やビジネスリーダーへの道
1級では戦略的思考や企業価値評価も学べ、人材価値がさらに高まります。
9.まとめ
ビジネス会計検定試験は、簿記とは異なり「会計を活用する視点」を育成する唯一の資格として重宝される存在です。3級で基礎理解を固め、2級で応用力を磨き、1級で実務的な分析力と理論力を獲得することで、企業や社会で役立つ会計力を体系的に身につけられます。特に、情報化が進む現代において、「読み解く会計力」はビジネスのあらゆる場面で求められており、この検定が与える効果と価値は非常に大きいといえるでしょう。
10.ホームページ
大阪商工会議所