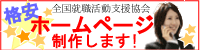55保育士試験
1.保育士試験とは
保育士とは、児童福祉法第18条の4に定められた国家資格であり、児童の保育および保護者への保育に関する指導を、専門的知識と技術をもって業として行う者を指します。
保育士の資格を取得する方法は主に二つあります。一つは、都道府県知事が指定した養成施設を卒業すること。もう一つは、保育士試験に合格することです。
特に後者は、養成施設を経ずとも国家資格を得られる、挑戦しがいのあるルートです。
保育士試験は筆記試験と実技試験の2段階で構成されており、筆記試験に全科目合格した者のみが実技試験を受験できます。
2.受験資格
受験資格の詳細については公式サイトに「受験資格詳細」として案内されていますが、代表的な要件は以下の通りです
養成施設卒業者:指定された保育士養成施設を卒業した者。
養成施設以外の者:高等学校卒業者で、児童福祉施設での実務経験が一定以上ある場合など、別途定められた条件を満たせば受験可能。
また、免除制度も設けられており、幼稚園教諭免許状保持者や他資格保持者に対する科目免除、合格科目の有効期限延長などの制度もあります。
3.試験日程(例年のスケジュール)
保育士試験は、例年「前期」と「後期」の年2回実施されます。
前期
筆記試験:4月第3週の土・日(令和7年前期は4月19日・20日)
実技試験:その後の6月最終週の日曜日(例:令和7年前期は6月29日)
後期
筆記試験:10月第3週の土・日(令和7後期は10月18日・19日)
実技試験:12月第1週の日曜日(令和7後期は12月7日)
4.試験地
試験会場については、申込時ではなく、受験票に記載される形で通知されるため、詳細な地名は受験票到着後に確認となります。
5.受験手数料
12,700円
6.試験内容(詳細)
筆記試験
筆記は9科目について行われ、マークシート形式で実施されます
科目一覧と配点・出題形式(令和7年前期例)
4月19日(土)
保育の心理学(100点、11:00〜12:00)
保育原理(100点、13:00〜14:00)
子ども家庭福祉(100点、14:30〜15:30)
社会福祉(100点、16:00〜17:00)
4月20日(日)
教育原理(50点、10:00〜10:30
)社会的養護(50点、11:00〜11:30)
子どもの保健(100点、12:00〜13:00)
子どもの食と栄養(100点、14:00〜15:00)
保育実習理論(100点、15:30〜16:30)
各科目で満点の6割以上が合格基準ですが、「教育原理」と「社会的養護」は両方とも6割以上得点しなければ合格とはなりません
実技試験
筆記試験に全科目合格した受験者のみが対象です。
実技は以下3分野のうち2分野を選択して受験します
音楽に関する技術:
課題曲2曲(例:「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」「証城寺の狸囃子」)を弾き歌いする演奏技術と表現力が評価されます。ピアノまたはギターで演奏。ギターは持参。演奏形態の制限(伴奏のみ、歌のみ等)は採点対象外となります。
造形に関する技術:
当日提示される保育場面を絵画で表現。表現力や構成、色使いなどが評価されます。使用可能な画材・持ち物の制限あり(鉛筆、色鉛筆など)
言語に関する技術:
物語から選び、3分間で幼児が集中して聴けるように話す表現技術を評価。声の出し方や話し方の工夫が問われます。
実技の配点は各50点満点です
7.合格後の流れと研修
合格後の流れについて、公式サイトに詳しい案内はありません。しかし、一般的なプロセスとして以下のステップが想定されます:
合格通知・免除適用:筆記・実技の合格科目については、マイページ等で通知される(例:前期実技試験結果は7月末に公開)
資格の登録:合格後、保育士として働くには各都道府県の保育士登録簿に登録する必要があります。
保育実務開始:保育施設等での実務に就き、資格を活かすことが可能になります。
8.資格取得のメリット
国家資格としての信頼性:児童福祉法に基づく国家資格であるため、安定したキャリア構築が可能です。
養成課程を経ないルートもある:養成施設に通わず、筆記+実技試験の合格で資格取得が可能で、多様な受験者に門戸を開いています。
科目免除・合格科目の有効期間:免除制度や合格科目の有効期限(数年間)により、複数年にわたって計画的に全科目取得できる点が魅力です。
再就職やキャリアの柔軟性:一度取得すれば生涯活用でき、結婚・育児・転職後の再就職にも強いメリットがあります。
9.まとめ
保育士試験は、児童福祉法に基づく国家資格取得のための試験であり、養成施設卒以外のルートを選ぶ者にとって重要な制度です。筆記試験(9科目)と実技試験(3分野から2分野選択)の2段階方式で、いずれも合格を得ることで資格が得られます。
受験資格には学歴や実務経験の要件があり、さらに科目免除や合格科目の有効期間など、合理的な制度設計がなされています。試験は年2回、前期は4月・6月、後期は10月・12月という流れで進行し、試験地は受験票による案内を待つ形式です。
資格取得後は、都道府県への登録を経て保育事業に従事できるようになり、生活やキャリアの変化にも柔軟に対応しうる生涯有効な国家資格という位置づけです。挑戦しやすく、かつ生涯にわたって価値のある資格として、多くの人にとって希望となる存在です。
10.ホームページ
一般社団法人全国保育士養成協議会