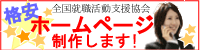57医師国家試験
1.医師国家試験とは(試験概要)
医師国家試験は、厚生労働省が医師法に基づいて毎年実施する 国家試験で、日本で医師として医療行為を行うために必ず合格すべき試験です。合格後に免許が交付され、医師としての業務が法的に認められます。出題は医学の基礎から臨床、公衆衛生まで幅広く、医師に必要とされる知識と技能の評価が目的です。
2.受験資格
受験資格は以下のいずれかに該当する者です:
学校教育法に基づく大学医学科を修了し卒業した者、または卒業見込みの者(臨床実習前に共用試験合格者含む)
医師国家試験予備試験に合格し、さらに 1年以上の診療・公衆衛生に関する実地修練 を経た者(令和8年3月10日までに完了見込み)
海外の医学校を卒業・医師免許を取得し、厚生労働大臣により同等以上の能力と認められた者
沖縄復帰以前の琉球政府医師法に基づいて医師資格を取得し、厚労大臣が認定した者
3.試験日程(例年のスケジュール)
第119回(2025年実施)は 令和7年2月8日(土)および9日(日) の2日間にわたり実施されました。合格発表は 3月14日(金)午後2時 に厚労省HPで行われました。
第120回(2026年)も同様、令和8年2月7日・8日 に開催予定です。
合格発表は例年 3月中旬、解答公開は 4月中旬頃 に行われます。
4.試験地
試験会場は 全国12都道府県 にまたがり、受験者は自分の最寄り会場(大学やホテルなど)に割り当てられます。具体的な実施地は以下の都道府県です:
北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県
東京都には受験者が集中するため複数会場が設けられることがあります。試験票に会場が記載されるため、受験直前に確認が必要です。
5.受験手数料
15,300円
6.試験内容(詳細)
▸ 出題形式と全体構成
2日間合計で約13時間40分、400問 が出題されます。
解答形式はマークシート方式で、五者択一、多肢選択(択二・三)、計算問題などが混在します。
目構成
出題は以下の3つの領域に分類され、複数のブロックに分割されています。
必修問題(基礎知識;80%以上の正答が絶対評価)
一般問題(医学総論・各論など)
臨床実地問題(症例や長文形式による設問)
各問題はそれぞれ点数が異なり、一般問題1点、臨床実地問題は3点という配点構成もあります。
▸ 合格基準・ボーダーライン
合格するためには以下をすべて満たす必要があります:
必修問題:80%以上の正答(絶対評価)
一般問題と臨床実地問題それぞれで、過去の実績に基づいた相対評価のボーダーをクリア(例:一般65%、臨床60%後半程度)
禁忌肢(誤答)を2問以下に抑える必要あり
近年の合格基準は、必修の正答率と問題別のボーダーの両方をクリアする厳密な評価方式になっています。
▸ 試験の傾向
近年では実臨床に即した ケーススタディ形式の長文問題、最新ガイドラインや公衆衛生的視点 を取り入れた実践的内容が増加しており、「暗記だけでなく応用力が問われる」傾向が強まっています。
7.合格後の流れと研修
合格後には厚生労働省から 医師免許 が付与されます。
続いて、2年間の初期臨床研修(医師臨床研修制度) が義務付けられており、診療スキルや実践的能力を高めます。
初期研修修了後は、後期研修や専門研修、専門医取得など、キャリアパスが広がります。
8.資格取得のメリット
医師国家試験に合格し医師免許を得ることは、日本の医療制度において 医療行為の法的根拠 となります。
合格率は例年 約90%前後 と比較的高いものの、医学部入学から国家試験までの長期間・高難度の学修を経た者が受験するため、取得の価値は極めて高いです。
免許取得後は、医療職としての責務を果たすだけでなく、公共医療、専門医、研究、行政、国際医療など多様な進路が開かれます。
9.まとめ
日本の医師国家試験は、大学医学教育の修了者を対象に 幅広い医学知識と臨床応用力を評価する、国家レベルの試験です。2日間にわたる400問の出題形式で、マークシート方式を採用しつつも、単なる暗記では対処できない事例分析や応用問題が増加傾向にあります。受験資格は医学部の卒業または予備試験+実地研修による特殊ルートが認められています。試験地は全国12都道府県に設置され、毎年2月上旬に実施されます。合格後は医師免許が交付され、初期臨床研修を経て専門医や公衆衛生医などさまざまな道を歩める、医学分野で最重要かつ国家資格としての重みを持つ試験です。
10.ホームページ
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ishi/