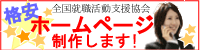68管理栄養士国家試験
1.管理栄養士国家試験とは
管理栄養士国家試験は、医療・福祉・学校・産業・行政など多分野で活躍できる管理栄養士になるために必須の国家資格試験です。栄養士とは異なり、 高度な栄養管理・栄養指導・給食管理などを業務とする者に与えられる、厚生労働大臣が認定する独占業務資格です。昭和62年(1987年)に第1回が実施されて以来、毎年制度が継続されています
2.受験資格
管理栄養士国家試験を受験するには、以下二つのルートがあります:
管理栄養士養成施設を修了した者:大学や専修学校など、厚生労働省指定の養成施設で所定の教育課程(通常4年)を修了した者
栄養士として実務経験を積んだ者:栄養士養成施設(2~4年制)を卒業後、一定年数の実務経験を経た者も受験可能です。例えば、2年制卒なら3年以上、3年制卒なら2年以上、4年制卒なら1年以上の実務経験が要件です。
なお、令和7年度より養成施設修了者は栄養士免許を経ずに直接受験が可能になるなど、制度の一部簡素化の動きもあります。
3.試験日程(例年のスケジュール)
管理栄養士国家試験は年1回、3月に実施されます。
例えば、令和8年(2026年)第40回試験は2026年3月1日(日)に実施予定で、合格発表は同年3月27日(金)午後2時に厚生労働省のウェブサイトで行われます。
4.試験地
試験会場は全国9都道府県で設けられ、北海道・宮城県・埼玉県・東京都・愛知県・大阪府・岡山県・福岡県・沖縄県で実施されます。各都道府県では大学や専門学校などを会場として指定されます。
受験票に具体的な会場が記載され、自ら選択することはできません。
5.受験手数料
6,800円
6.試験内容(詳細)
管理栄養士国家試験は、200問・マークシート方式で出題され、午前・午後の2部構成で実施されます。
出題科目と出題数
午前(2時間25分)には以下が出題されます:
社会・環境と健康(16問)
人体の構造と機能および疾病の成り立ち(26問)
食べ物と健康(25問)
基礎栄養学(14問)
応用栄養学(16問)
午後(2時間40分)には:
栄養教育論(13問)
臨床栄養学(26問)
公衆栄養学(16問)
給食経営管理論(18問)
応用力試験(状況設定問題)30問
出題形式
すべてがマークシート方式(1問1点)で出題され、応用力試験は状況設定型の問題です。
合格基準
200点満点中、60%以上(120点以上)が目安であり、総合点のみで判定され、科目別の足切りはありません。ただし確実に合格するには70%以上を目指す受験生が多いようです。
7.合格後の流れと研修
合格者には合格証書が送付され、管理栄養士としての国家資格が交付可能になります。さらに、免許申請を地方自治体に行うことで正式に管理栄養士の免許を取得します。
資格取得後は医療施設や学校、福祉施設で栄養管理や給食の運営、健康増進活動、産業・行政での栄養政策など幅広い業務へ従事できます。加えて、管理栄養士が対象の研修プログラム(例:栄養改善・給食管理等)を受けることでスキルアップ・キャリア拡張も可能です。
8.資格取得のメリット
管理栄養士資格は、以下のような利点があります:
法的専門性を担保する国家資格:厚生労働大臣の免許により、医療・公衆衛生・福祉等における信頼性が高い立場を得られます。
幅広い活躍領域:病院・学校・保健所・食品企業など、多様な分野で栄養支援が求められ、職域が広いことが強みです。
社会的需要の高さ:高齢社会や生活習慣病対策の観点から、専門性のある管理栄養士の役割が今後さらに重要となります。
明確な試験制度:1日で200問を解く明瞭な構成と60%合格率により、学習目標がはっきりしています。
質の高い養成と試験制度:改定が行われる出題基準によって、時代の変化に即した知識が反映されており、教育の質も伴っています。
9.まとめ
管理栄養士国家試験は、栄養士よりも高度かつ専門的な栄養指導・管理を行う国家資格です。受験には養成施設修了または所定の実務経験が必要で、年1回3月に全国9都道府県で実施されます。科目は9つに分かれ、合わせて200問が出題され、合格には60%以上の得点が求められます。合格後、免許申請を経て正式に管理栄養士として活躍でき、保健・医療・福祉・教育など幅広い分野で信頼される専門職としてのキャリアが開かれます。高齢化や生活習慣病への対応が求められる現代において、管理栄養士の資格を持つことは社会的にも価値ある選択となります。
10.ホームページ
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/