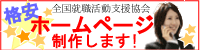75みんなの結婚検定
1.「みんなの結婚検定」とは(試験の定義・趣旨)
「みんなの結婚検定」は、一般財団法人 全日本情報学習振興協会が運営し、結婚・恋愛・家族・法律・社会的要因など、結婚をめぐるさまざまな知識・意識を体系的に問う検定試験です。
この検定の目的は、少子化・晩婚化・非婚化が進展している現代社会において、結婚や家族に関する正しい知識・意識を広く普及させるとともに、受験者自身が結婚観や人生設計を改めて考える契機とすることにあります。
特に、未婚者にとっては「自分の結婚に対する価値観や方向性を考える材料」に、既婚者にとっても「今までの結婚観再点検」あるいは「配偶者との生活をどう構築していくかを見直す契機」にという位置づけが打ち出されています。
また、結婚相談所スタッフ・婚活アドバイザー・ウェディング業界関係者などにも、専門性向上のために受験を促す案内がされており、業界内での知識基盤を共通化・補強する目的も想定されています。
このように、「みんなの結婚検定」は純粋な趣味・知識関心だけでなく、婚活支援・ブライダル業界など実務にも接点を持たせる意図を含む検定です。
2.受験資格
「みんなの結婚検定」に関して、公式に「受験資格」を限定するような年齢制限・学歴制限・前提条件などは設けられていません。
3.試験日程(例年スケジュール)
試験は年に複数回実施されます。ただし、種別(認定区分)によって回数や時期に違いがあります。
「結婚アドバイザー認定試験(上級)」:年に 2回 開催。たとえば、6月(6月下旬)および翌年3月に実施されることが過去例として示されています。
「結婚エクセレント認定試験(中級)」:例年 1回 開催。9月頃に実施される回が案内されています。
「結婚スタンダード認定試験(初級)」:こちらも 1回程度 の開催が予定されており、開催月は未固定(未定)であると案内されていることが多いです。
試験時刻も種別により異なります。アドバイザー認定では午前10時から午前11時45分まで(試験時間:90分)という事例が案内されています。
エクセレント認定試験は午前10時開始、午前11時15分まで(試験時間:75分)という例が示されており、スタンダード認定試験は午前10時開始、午前11時(試験時間:60分)という案内もあります。
なお、オンライン試験やCBT方式の時間枠は、公開会場試験と異なる場合があるため、このように、例年スケジュールとしては春(3月)・初夏(6月)・秋(9月)などに分かれて開催される傾向があります。
4.試験地(受験会場・形式)
「みんなの結婚検定」では、次のような受験形式・試験地が選択可能です。
4-1 公開会場試験(紙方式)
大学・施設等で指定の会場にて実施される方式です。受験者は配布された紙の試験問題をマークシート方式で解答します。受験票に写真を貼って所定席で受験する形式です。
4-2 CBT形式(テストセンター方式)
全国の提携テストセンターにおいて、パソコンとウェブカメラを備えたCBT形式で実施されます。会場利用料が別途加算される場合があります。
4-3 オンライン(在宅受験)形式
自宅等、受験者の任意の場所からオンラインで受験する方式も用意されています。受験者は自前のパソコンおよびウェブカメラ(外付け・広角対応)を準備し、オンライン試験システムを通じて受験します。協会側からカメラ貸出を行うケースもあります(貸出分は送料が発生することがあります)。
このように、受験者は自身の環境・利便性に応じて、公開会場・CBT会場・オンラインという選択肢から受験形式を選べる柔軟な構成となっています。
5.受験料
「みんなの結婚検定」の受験料金は、認定区分によって異なります。公表されている主な受験料は以下の通りです。
結婚アドバイザー認定試験(上級):11,000円(税込)
結婚エクセレント認定試験(中級):6,820円(税込)
結婚スタンダード認定試験(初級):4,950円(税込)
なお、CBT方式で受験する場合は、会場利用料として プラス2,000円 が加算されます。
また、クレジットカードで支払えるほか、分割払いが可能な案内も出されています。
なお、学生割引が適用されるケースも案内されており、学生であれば受験料の優遇措置を受けられる可能性があります。
6.試験内容(詳細)
試験内容は、認定区分(スタンダード・エクセレント・アドバイザー)ごとに共通部分と発展部分で構成されています。出題形式はすべて マークシート方式 です。
以下に、各認定区分の出題構成・課題・出題範囲を整理して説明します。
6-1 認定区分と概要
| 認定区分 | 試験時間 | 問題数 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| スタンダード認定試験(初級) | 約 45 ~ 60分 | 約 40問 | 合計の得点で70%以上(目安) |
| エクセレント認定試験(中級) | 約 60分 | 60問 | 合格基準:70%以上 |
| アドバイザー認定試験(上級) | 約 90分 | 約 80問 | 合格基準:70%以上 |
スタンダード・エクセレント・アドバイザーともに、第1課題と第3課題は共通出題範囲とされており、エクセレント・アドバイザーで第2課題(発展分野)を追加で問う構成となっています。
以下、課題別に出題内容を詳しく見ていきます。
6-2 出題課題・範囲
出題は「第1課題」「第2課題」「第3課題」に区分され、それぞれテーマ別の知識を問う問題群で構成されます。
第1課題(共通範囲)
すべての認定区分に共通して出題される範囲です。以下の主要テーマが含まれます。
既婚者の幸福感と意識
- 結婚と幸福感の関係
- 結婚相手との出会い方と出会いの傾向
- プロポーズ、結婚の決断過程
- 結婚費用・家計負担等
結婚願望と希望条件・結婚観
- 未婚者の結婚願望や意識動向
- 希望する結婚相手の条件(年齢・年収・性格・生活観等)
- 結婚観(価値観・優先度・妥協意識)
- 既婚者の条件妥協事例
恋愛・交際と婚活
- 恋人の有無と結婚意識
- 恋愛関係の進展過程
- 出会い手段(婚活、SNS、マッチングアプリ等)
- プロポーズの意義や方法
- 非対面出会いの実態(出会いアプリ利用など)
結婚・仕事・子ども・家族
- 結婚後の仕事継続(特に女性の場合)と家事・育児の両立
- 配偶者の仕事・収入と家庭構造
- 子どもを持つこと、育児に関する意識
- 親との同居・家族構成・世代間関係
結婚・再婚・離婚の現状
- 結婚・再婚・離婚の年次変遷
- 非婚化・晩婚化の背景と傾向
- 未婚・既婚者の年収・社会経済的背景
- 再婚・離婚の実態
結婚・離婚と法律
- 婚姻制度、婚姻届
- 夫婦別姓制度の議論
- 共同親権・子どもの法的保護
- 離婚制度、再婚制限、相続・財産分与など
- 結婚式・披露宴に関するルール・慣習
各認定区分では、この第1課題問題が基礎となります。
第2課題(発展分野・アドバンス領域)
この課題は「エクセレント」および「アドバイザー」向けの発展的な知識を問う範囲が中心です。スタンダード認定試験では通常出題されません。
主な出題テーマは次の通りです:
婚約と結納
- 略式結納・食事会形式
- 結納手順・儀礼
- 婚約記念品・エンゲージリング
結婚式・挙式スタイル
- 神前式、キリスト教式、人前式、仏式などの形式
- 個性的・テーマ式挙式や海外挙式など多様な形式
結婚式・披露宴の会場・運営
- 式場選定、挙式日・月の傾向
- 披露宴構成・演出・進行
新婦の衣装
- ウェディングドレスのシルエット、素材
- カラードレス、和装および和装小物
新郎の衣装
- 和装・洋装の選び方・形式
結婚式・披露宴の定番演出
- 挙式演出、披露宴演出・演目
- 招待者構成、進行の工夫
新婚旅行
- 人気旅行先、旅行形態
- 旅費・支出の傾向
誕生石・ダイヤモンド
- 石言葉、選び方
- ダイヤモンドの品質評価基準
結婚準備に関する美容・ケア
- ブライダル美容施策(エステ・肌ケア等)
その他結婚関連知識
- 結婚ギフト、引出物、慣習・風習など多角的知識
これらのテーマは、ブライダル産業・式運営・婚礼プロデュースに即した知識を含むため、業界関係者やアドバイザー志望者にとっては重要な知識領域です。
第3課題(法律・制度・応用問題)
この課題も全認定区分共通範囲ですが、出題レベル・比率は認定区分に応じて変動する可能性があります。主として、法律・社会制度に関する応用問題が扱われます。
第3課題のテーマ例には以下があります:
婚姻届け・戸籍制度
夫婦別姓制度、共同親権制度
同棲・事実婚・パートナーシップ制度(将来的導入議論含む)
憲法と結婚制度、法的規範と婚姻制度
相続・財産分与・婚姻費用・慰謝料などの法的制度
結婚式・披露宴における契約・法的責任
6-3 出題の特色・傾向
問題は、結婚・家族に関する 統計データ・アンケート結果 に基づく出題が多く見られます。例えば、内閣府「男女共同参画白書」や一般財団法人日本結婚総合研究所、明治安田総合研究所などの調査データが根拠として用いられることがあります。
実際のデータや傾向を読み取って回答を選ばせるタイプの設問(グラフ・図表を参照させる問題も含む可能性)も出題されることがあるようです。
出題はすべてマークシート形式で、記述式は採用されていません。答案の正誤を選択形式で答える方式です。
難易度としては、スタンダード・エクセレント・アドバイザーでレベル差があり、上級ほど専門性・実践性を含む出題が多くなります。特に第2課題分野は、アドバイザー認定受験者向けの知識要求が高いとされています。
6-4 合格基準および合否判定
各認定区分において、合格基準は「正答率70%以上」が目安とされています。
合格発表後、受験者は出題された問題と自身の解答、および正答を確認できる期間があります(試験後約1週間から1か月程度)。
7.合格後の流れと研修(認定制度)
合格後の流れについては、公式情報として明確に「必須研修」があるという記述は限定的ですが、いくつかの仕組みが案内されています。
合格者には「合格者特典」が設けられており、認定証の授与などが含まれます。
また、合格者を対象とした追加的な研修や活用プランが案内されている可能性があり、認定者として活動支援を設けようという意図が示されています
業界関係者(結婚相談所・婚活支援者等)にとっては、アドバイザー認定取得後、ビジネス活動やコンサルティング活動に際して、所定のノウハウ活用・信用力向上を図る流れが想定されます。
8.資格取得のメリット
「みんなの結婚検定」を取得することには、以下のようなメリットが考えられます:
知識・教養の習得
結婚・家族・法律・社会動向に関する幅広い知識が体系的に得られるため、自己理解・人生設計の質を高めることができます。特に、結婚観や価値観を整理する教材的効果があります。
信頼性・客観性の証明
公共性のある検定を取得することで、婚活アドバイザー・結婚相談所スタッフ・ブライダル業界関係者などの立場で、顧客やクライアントから信頼を得る材料になります。
差別化と専門性アピール
同業他者との差別化を図るため、検定取得は自己ブランディングの一助となります。特にアドバイザー認定取得者は、専門知識を有するシンボルになります。
実務知識の活用
結婚式企画・ブライダルプランニング・婚活支援などの実務に直結する知識(式典・挙式スタイル・演出・法制度等)が問われるため、実践的活用が可能です。
ネットワーク・認定者コミュニティ
合格者同士、認定者コミュニティや情報交換の場が提供される可能性があり、業界交流・知見共有が得られる可能性があります。
啓発活動・普及活動
社会的な観点から、結婚や家族に関する知識啓発を担う役割を果たすことができ、地域・自治体などとの連携機会を得やすくなる可能性があります。
自己ブランディング
個人的に「結婚・ライフプラン支援に強い」「家族教育に造詣が深い」などの印象を与えるための資格として活用できます。
ただし、この資格の有効性・市場評価は、今後の普及度と認知度に依存する部分も大きいため、取得自体が即ビジネス化を保証するものではありません。
9.まとめ
「みんなの結婚検定」は、結婚・家族・恋愛・法律・社会動向などを題材とした知識を体系的に検定する試験で、現代社会の少子化・晩婚化傾向を背景に設立されています。受験資格に大きな制限はなく、誰でもチャレンジできる形式が特徴です。年に複数回、スタンダード・エクセレント・アドバイザーという区分別に試験が実施され、公開会場・CBT(テストセンター)・オンライン方式の受験が可能です。
試験内容はすべてマークシート形式で、共通の出題分野(第1課題・第3課題)に加えて、中上級区分では結婚式運営・婚礼知識・発展的法律知識などの第2課題が加わる構成となっています。合格基準はおおむね正答率70%以上が目安とされ、合格後は認定証の授与や、将来的には認定者向けの支援・研修が想定されています。
この検定を取得するメリットとしては、結婚・家族・ライフプランに関する知識を深められる点、婚活支援やブライダル業界での信頼性向上や差別化が図れる点、実務知識が得られる点などが挙げられます。