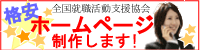81公害防止管理者等国家試験
1.公害防止管理者等国家試験とは
公害防止管理者等国家試験は、法律により設置が義務づけられた「特定工場」における公害防止組織の一員として、公害の予防、運転・維持管理、検査などを担う専門的な人材を資格として認定する国家試験です。公害防止管理者等国家試験は、経済産業省所管の国家試験であり、一般社団法人 産業環境管理協会が経済産業大臣の指定を受けて実施しています。
資格は 全部で13区分に分かれており、大気・水質・騒音・粉じん・ダイオキシンなど公害の種類によって専門区分が設定されています。さらに主任管理者という区分もあり、特定工場における上位の管理者としての役割も含まれます。
2.受験資格
受験資格に関する制限は一切なく、年齢、性別、学歴、職歴などに関係なく、誰でも受験できます。
また、国家試験以外の選択肢として「資格認定講習」を受講し修了試験に合格する方法もありますが、こちらには受講に際して一定の技術資格や学歴/実務経験の制限が課されることがあります。
3.試験日程(例年のスケジュール)
試験スケジュールは例年以下のように進行します:
官報への公示:例年6月初旬(令和7年は6月5日)
インターネット申し込み:7月1日開始、7月末(31日)まで受付
受験票発送:9月上旬に郵送で送付
試験日:例年10月の第1日曜日(令和7年度は10月5日)
合格者速報掲載:11月中旬(例:令和7年は11月17日頃)
官報による正式合格公示/合格証書発送:12月中旬(例:令和7年は12月15日)
4.試験地
試験地は全国主要都市で実施されます。札幌市、仙台市、首都圏(東京・神奈川・埼玉を含む)、愛知県、京都/大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市およびその周辺地域で実施されます。会場確保の都合により、他の地域で実施されることもあるため、受験者は試験会場を選べず、受験票で通知された会場に従う必要があります
5.受験料
区分により手数料が異なりますが、代表的な例は以下の通りです(非課税):
大気関係第1種、水質1種、ダイオキシン類、公害防止主任管理者など:12,300円
大気関係第2種などその他区分:11,600円
6.試験内容(詳細)
区分と科目体系
試験は共通科目(公害総論)と各区分固有の科目群で構成されます。たとえば「大気関係第1種」であれば、大気概論・大気特論・ばいじん・粉じん特論など、複数の科目を組み合わせて出題されます。
科目別問題数(令和6年度の例)
以下は令和6年度(2024年度)の科目別出題数の一例です:
公害総論:15問
大気概論:10問
大気特論:15問
ばいじん・粉じん特論:15問
大気有害物質特論:10問
汚水処理特論(水質):25問
騒音・振動概論:25問
ダイオキシン類特論:25問
など、合計するとかなり多岐かつ広範な科目が設定されています。
試験時間割の例
各区分の科目ごとに時間が割り当てられ、たとえば大気関係第1種では以下のようなスケジュールになります:
9:35~10:25:公害総論
11:00~11:35:大気概論
12:45~13:35:大気特論
14:10~15:00:ばいじん・粉じん特論
15:35~16:10:大気有害物質特論
16:45~17:20:大規模大気特論
科目ごとに制限時間が明確に設定され、一度入室後の途中退出や遅刻は原則不可とされています。
合格基準と合格率
科目合格制度:特定の科目に合格すれば、その科目については最長3年間、再受験時に免除申請可能です。
試験区分合格:構成科目すべてに合格が必要。区分合格で資格証書が交付されます。
合格率(令和6年度全体平均):25.9%(申込者22,763人、受験者20,263人、合格者5,244人)
科目別では、ダイオキシン類特論(67.6%)、概論(62.2%)、水質関係技術(60.0%)が高く、公害総論(30.4%)や大気関係技術特論(20.4%)などが低い傾向です。
7.合格後の流れと研修
合格後の扱い
合格者には合格証書が官報で公示された後(12月中旬)、簡易書留で送付されます
この合格証書により資格が証明され、免許や登録手続きは不要、永年有効の資格です
科目免除制度
科目合格に基づく免除:科目単位で合格した場合、3年以内に同一区分を受験する際には、その科目が免除できます
区分合格による共通科目免除:既に資格を取得した区分と共通する科目が、新たな区分受験時に免除される制度もあります(期間無制限)
なお、免除制度は講習(研修)にも適用され、共通する講義の受講が免除される場合があります。ただし修了試験は全科目受ける必要があります。
8.資格取得のメリット
法的義務への対応:「特定工場」では公害防止管理者の選任が法律で義務づけられており、資格保持者はその要件を満たすことができます。
専門性の証明とキャリア向上:工場の公害防止運営の専門家として認められ、昇給・昇進・手当対象となる場合もあります
科目免除制度で効率的な資格取得が可能:ステップアップ形式で別区分取得が有利になり、キャリア形成を助けます。
企業・組織への信頼向上:環境責任の明示や、ISO等の内部体制強化にも資する人材として期待されます。
9.まとめ
公害防止管理者等国家試験は、公害防止における法律的な要請に応えるための専門的資格制度であり、受験資格がなく誰でも受験できる国家試験です。全13区分に分かれた幅広い専門性を持つ資格であり、具体的な出題科目や数・時間割も試験区分ごとに詳細に定められています。
試験は年1回、10月上旬に全国主要都市で実施され、科目合格制度や区分合格により柔軟に取得が可能です。
合格率は区分による差があるものの、全体平均で約25.9%(2024年度実績)と高い難易度がうかがえます。合格後に免許登録手続きは不要で、永年有効の資格証書が発行されます。
制度的なメリットとしては、法律上の選任義務への対応、人事評価の材料、内部統制や環境管理体制の強化など、資格取得者は工場運営や企業環境責任において非常に価値ある存在として位置づけられます。
10.ホームページ
一般社団法人産業環境管理協会